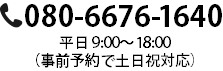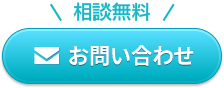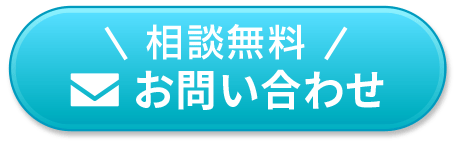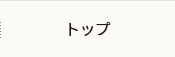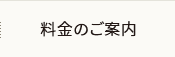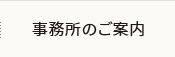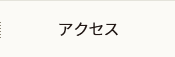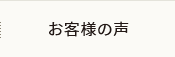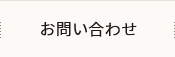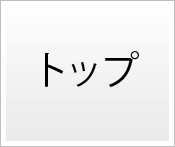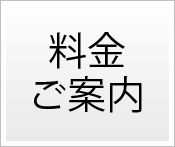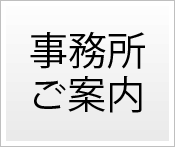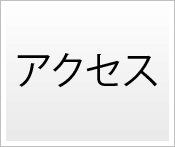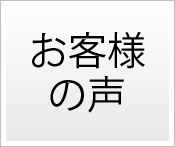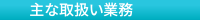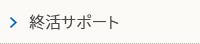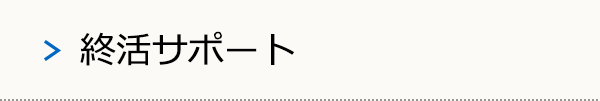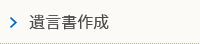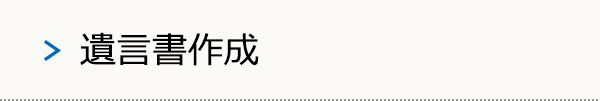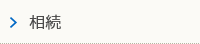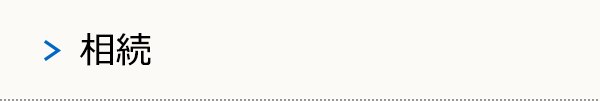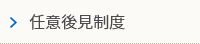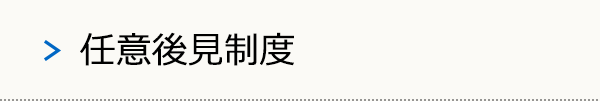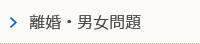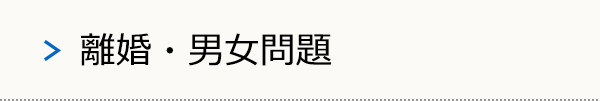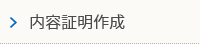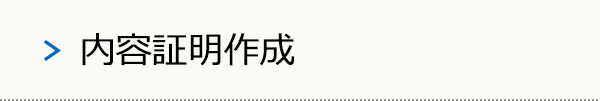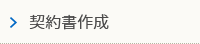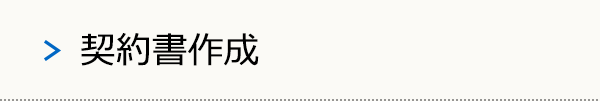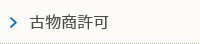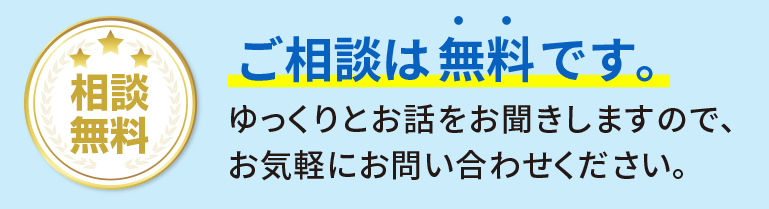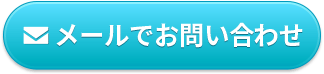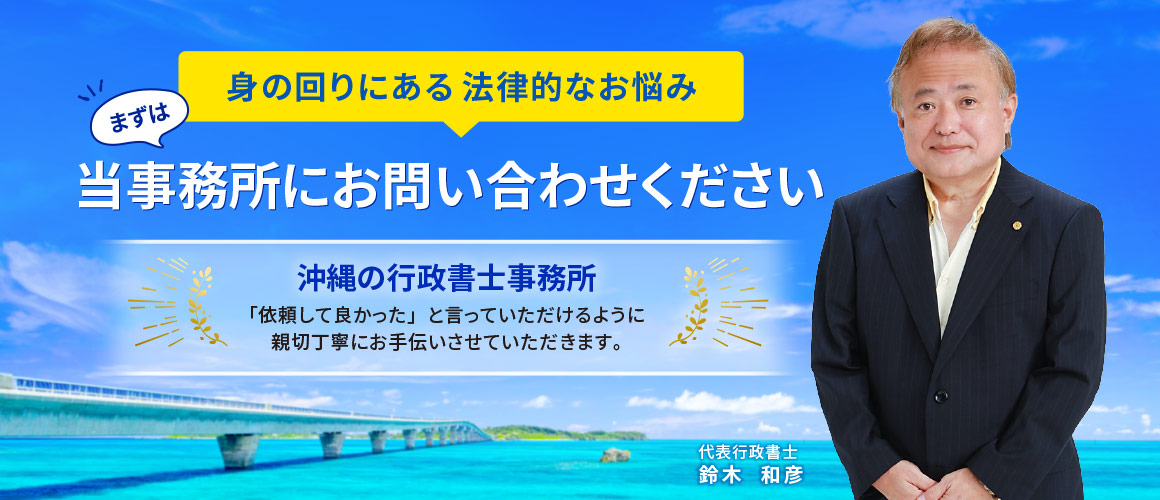
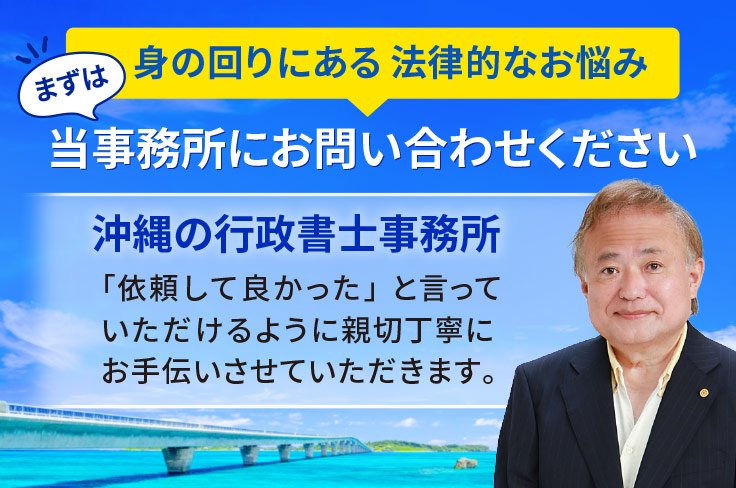
任意後見制度
いまは元気で、判断能力がしっかりしている人が、将来、判断能力が衰えて、不十分になった時に備えて、
自分に代わって事務手続きなどをやってくれる人と、どんな内容を自分に代わってやって欲しいのか、
事前に契約をしておく制度を「任意後見制度」といいます。
そして、自分に代わって事務手続きなどを、やってくれる人のことを「任意後見受任者」といいます。
「任意後見契約」は、重要な契約なので、公証人役場での、作成が義務付けられていますが、
契約しても直ぐには、効力が発生しません。
将来に、自分の判断能力が衰えて、不十分になって、認知症と判断されたら、家庭裁判所で、
「任意後見監督人」が選任されて、はじめて「任意後見契約」の効力が発生するのです。
そうなると、「任意後見受任者」は「任意後見人」となり、「任意後見監督人」の監督の下で、
先に決めた、「任意後見契約」の内容に従って、諸々の事務を開始します。
任意後見契約には、将来型・移行型・即効型の3種類の利用形態があります。
| ①将来型 |
本人の健康状態もよく、判断能力のしっかりしているうちに契約を結んでおき、将来、 自分の判断能力が衰え、不十分になった時に、任意後見契約による効力を発生させるもので、 財産管理委任契約を結ばずに、任意後見契約だけを結んでる形態です。 この形態では、本人の健康状態や判断能力の確認をするため、「継続的な見守り契約」を 結んでおくことが重要となります。 |
| ②移行型 |
任意後見契約と一緒に、本人と「財産管理委任契約」を締結することで、契約の時点から、 「任意後見契約」の効力が発生するまでの期間も、様々な事務を任意後見受任者に頼むことが できます。いわば、判断能力はしっかりしているけれど、体力の低下などで、 金融機関などへ行くのが大変だという人です。 |
| ③即効型 |
判断能力が低下している状態の本人と契約し、時間をおかずに「任意後見契約」の効力を 発生させる形態です。「任意後見契約」の締結後にすぐ、家庭裁判所で「任意後見監督人」の 選任をしてもらい、「任意後見人」による事務を開始します。 本人の意思能力があり、この受任者と契約をしたいという意思が、公証人から見て、 確認できる限りは、即効型の「任意後見契約」を結ぶことができます。 しかしながら、あとになって、任意後見契約締結時における、本人の意思能力の有無について、 争われる可能性もあるので、無理して即効型の任意後見契約を結ぶのではなくて、 法定後見制度の利用を優先すべきです。 |
任意後見人の業務は、本人の財産管理と本人の生活や療養に関する支援などで実際に介護をしたり、
食事の世話をするといったことまで助けてくれるわけではないので、注意が必要です。
また、これらの制度は、あくまでも契約に基づいてなされるものなので、契約の締結時に、本人の判断能力が
あることが必要になるので、そのとき、すでに、認知症の診断を受けるなど、判断能力が衰え、
不十分になってしまった場合には、法定後見人制度を利用せざるを得なくなってしまうことです。
遺言書を書くほど財産はないけど、自分が死んだら、いま住んでる家や土地は?預貯金?葬儀は?
お墓は?家の片づけは?様々な契約の解除や費用の清算は?遺産相続は?
残された家族は暮らしていけるのだろうか?年金の手続きは自分でできるのだろうか?
などなど、様々な不安や疑問でモヤモヤしてきます。
そんな場合、モヤモヤ感をスッキリとさせるには、「死後事務委任契約」を結びます。
「死後事務委任契約」とは、聞きなれない言葉ですが、自分が死んだあとに発生する、
遺体の引取りに始まって、葬儀・火葬・納骨遺品の整理など、その他色んな死後の事務手続きについて、
信頼できる人に責任をもってやってもらえるように、事前に契約しておくことをいいます。
それじゃ、「遺言書に書いておけばいいんじゃないのか」って、思いますよね。
しかし、遺言書にかける内容は法律で決まっていて、「自分の財産を誰に、どうやって分けるのか」、
それを決めて書くためのモノなんです。そんな関係で、自分の死んだ後の様々な事務手続きについて、
希望がある場合は、「死後事務委任契約」を結んでおくべきです。
任意後見制度とは、本人の財産状況、家族関係、生き方、考え方、お金の使い方など、
希望や意向を十分に聞いたうえで、「任意後見契約」「見守り契約」「財産管理委任契約」
「死後事務委任契約」「遺言」などを上手く組み合わせて使っていくものだと思います。
任意後見契約だけに限らず、不安や疑問があれば、当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。